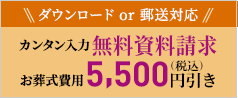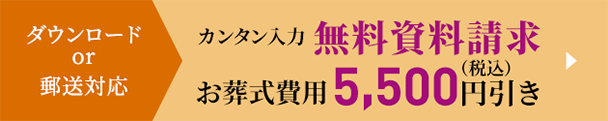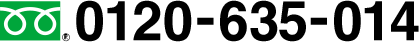曹洞宗の概要と通夜・葬儀・マナーを解説
お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
この記事は
「イオンのお葬式」
が書いてます
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
宗派の概要と通夜・葬儀
- 更新日:2022.04.28
- 宗派の概要と通夜・葬儀
曹洞宗の概要と通夜・葬儀・マナーを解説

曹洞宗について
| 宗名 | 曹洞宗 |
|---|---|
| 本尊 | 釈迦牟尼仏 |
| 宗祖 | 道元禅師(1200~1253年) |
| 本山 | 大本山永平寺・大本山總持寺(両大本山) |
| 主な教典 | 『摩訶般若波羅蜜多心経』『修証義』『妙法蓮華経観世音菩薩普門品』『妙法蓮華経如来寿量品』『大悲心陀羅尼』『甘露門』『参同契』『宝鏡三昧』『舎利礼文』等 |
| 主な祖録 | 『正法眼蔵』『伝光録』『永平広録』『永平清規』『普勧坐禅儀』『正法眼蔵随聞記』等 |
枕経の意義
2.jpg)
お釈迦様が死を迎えようとした時、お弟子様たちに最後の説法として『遺言』の『教え』を説かれました。曹洞宗の枕経では基本的にその内容をまとめた『遺教経』を読誦します。
故人さまが、お釈迦様と同じように、ご遺族に対する遺言として遺教経を唱えるという意味で、故人さまに代わってご住職がお経を唱えます。そこでは、故人さまが臨終間際のお釈迦様であり、ご遺族はお釈迦様のお弟子様だと捉えることができます。お釈迦様がお亡くなりになっても、お弟子様たちがその心を深く引き継いでいった姿にならい、お釈迦様の最後の教えとご縁を結び、心の拠り所として実践していくための大切な仏事となります。
通夜式の意義
お釈迦様は、紀元前383年、2月15日の満月の夜、北インドのクシナガラという所で入滅(逝去)されました。その夜から7日間、お弟子様たちは、お釈迦様を偲び、一晩中お釈迦様が生前説かれた教え(法)を語り続けられたといわれます。これが仏教における通夜の起源です。曹洞宗の通夜式ではそのお弟子様たちの姿にならって、お釈迦様の教えである「正伝の仏法」を伝えるため道元禅師様が書き著した『正法眼蔵』をもとにする『修証義』を、基本的にご住職とともにご遺族も一緒に読誦します。また、ご遺族におかれては、通夜式の後も故人さまとともに一晩を過ごし、お釈迦様のお弟子様たちのように、故人さまを偲び、思い巡らせることが伝統とされています。
葬儀の意義
1.jpg)
生命には必ず限りがあり、一旦生命が尽きれば、決して蘇ることはありません。しかし、その人に本来具わっている生命の根源である本性(霊魂)は消え去ることはなく、次の生へと引き継がれていくと言われます。これを輪廻転生と言います。
この輪廻転生があるがゆえに、曹洞宗の葬儀では故人さまの死後の安寧を祈ります。次の生が無事安心でありますようにと願い、故人さまには改めて仏・法・僧の三宝に帰依していただき、お釈迦様のお弟子様となっていただきます。そのためにご住職から仏弟子となる誓い「十六条の仏戒」を授けていただき、その証明となる戒名とお血脈をいただきます。これが葬儀式の中で一番重要とされる授戒式です。授戒が終わり仏弟子としての旅立ちの準備が整った後、ご住職から、生前の徳を讃え、成仏のためのお諭しと、励ましを込めた「引導」をわたしていただきます。この引導式も授戒式と並ぶ重要な儀式となります。
また、親族やご会葬の皆様方からはご冥福を祈る言葉(弔辞・弔電)をいただきます。さらに、焼香とともに、故人さまが成仏するための諸仏によるお導きをお願いし、次の生の安らぎを祈っていただきます。
戒名の意義
.jpg)
お戒名とは、仏弟子としての名前となります。お釈迦様がお悟りを開かれた後、俗名のゴータマ・シッダルタから「シャキャムニ・ブッダ」や「釈迦牟尼仏」と尊称されるようになったことがお戒名の淵源となり、日本では、出家した僧や受戒して仏弟子となった人は、俗名をお戒名に改めるようになりました。そのために必要なのが仏弟子となるための誓いである「十六条の仏戒」であり、それをいただく儀式が授戒式となります。受戒をして正統な仏弟子としての証明であるお戒名をいただかれた皆様には、「お血脈」も授けられることになります。
お血脈は中国唐代の禅宗で始まったと言われます。お釈迦様から始まり、インド・中国・日本の代々の代表となるお弟子様方の名前が記された紙を折りたたんだものです。その名前の最後はご住職に至り、その次に故人さまの戒名を書き記し、お釈迦様から故人さままでを一本の朱い線(血脈)で結びます。この系図が正統な仏弟子となったことの証明書となります。
曹洞宗のお戒名はこの仏戒授与と血脈授与により成り立っています。
焼香の回数
1.jpg)
曹洞宗のお焼香の回数は基本的に二回とされています。最初のお焼香は「正念のお焼香」と考えます。「正念にしみる」という言葉のとおり、まさに礼拝には正念がこもっていなくてはなりません。真剣であれば正念は一回で足りるはずで、曹洞宗では二回目からのお焼香を、「従香(じゅうこう)」と呼びます。従香は一回目の正念を、その形のままさらに大きく深くするために添えるお香となります。
具体的な作法としては、焼香台のある仏前に進み、焼香台の二、三歩手前でご本尊、故人さまの遺影、さらに、お位牌を仰ぎ、軽く一礼します。焼香台の前に進み、右手でお香をつまみ、軽く左手を添えるようにして額のところまで持って行き、いただいてゆっくり念じてから火中に薫じます。さらに二度目は、先のお香に添えるようにして、額にいただかずに火中に薫じます。お焼香をし終わったら、故人さまの冥福を祈り、お数珠を両手にかけて合掌・礼拝します。
他の宗旨・宗派をみる
その他
ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております