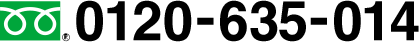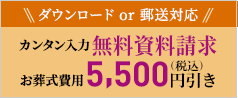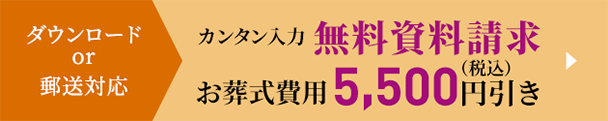四十九日について - 意味や数え方、服装など
お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
この記事は
「イオンのお葬式」
が書いてます
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
初めての喪主の方へ
- 更新日:2025.06.27
- 初めての喪主の方へ
四十九日について - 意味や数え方、服装など

大切な人とのお別れを経たあと、悲しみとともに訪れるのが「現実的な手続きや準備」の数々です。中でも、仏教の習わしとして広く行われているのが「四十九日法要」。
これは、故人の魂があの世へ旅立つまでの節目とされる重要な儀式であり、遺族や親族が集い、冥福を祈る大切な時間でもあります。
とはいえ、葬儀の後すぐに日常へ戻る中で、四十九日の準備を一人で進めるのは大変なものです。「何をいつまでにやればいいのか」「マナーや手配はどうするのか」など、不安や疑問を抱える方も少なくありません。
本記事では、四十九日法要までにやるべきことを時系列でわかりやすく解説します。ご遺族の心の整理と実務の両面をサポートできる内容をお届けします。
四十九日法要とは?その意味と役割
四十九日とは仏教用語のひとつで、命日から数えて49日目に行う追善法要のことを指します。なぜ49日なのかといいますと、仏教では人が亡くなるとあの世で7日毎に極楽浄土へ行けるかの裁判が行われ、その最後の判決の日が49日目となるためです。(七七日[なななぬか・しちなのか]と言われることもあります。)
従来は裁判が行われる7日毎に法要を行うものとされていましたが、現代では7日ごとに法要を行うのは難しいため、最初の裁判である「初七日(しょなのか)」と、最終裁判にあたる「四十九日」のみ法要を行うというのが一般的になりました。※「初七日法要」について詳しくはこちらのページをご覧ください
四十九日の数え方・実施日
数え方と実施日は、一般的には亡くなった日から数えて49日目となります。
(例:5月1日 命日 → 6月18日 四十九日)
地域によっては亡くなる前日を1日目とする数え方もあるので、その地域や宗派にあわせて考えましょう。
また、本来は49日目に法要を行うのが良いのですが、平日に当たってしまいご家族・ご親戚が集まりにくい場合は土日にずらすことも出来ますが、その場合は四十九日に該当する日よりも後に倒すのではなく前に繰り上げましょう。
初七日から続く法要の流れ
仏教では、人が亡くなった後の49日間を「中陰(ちゅういん)」と呼び、この間に故人の魂が次の世へ向かうと考えられています。中陰の間には、7日ごとに「追善法要(ついぜんほうよう)」を行い、故人の冥福を祈ります。これが「七七日(しちしちにち)」、つまり7日×7回=49日にわたる法要の流れです。
以下に、各法要の意味とタイミングを整理してご紹介します。
初七日(しょなのか)[亡くなってから7日目]
亡くなった日を1日目と数えて7日目に行う法要で、最も重要な節目のひとつです。
この日には、故人が三途の川のほとりで最初の審判を受けるとされ、その審判が無事に通るよう遺族が祈ります。
現在では、葬儀と同日にあわせて行う「繰り上げ初七日法要」として行われることがあります。
二七日(ふたなのか)〜六七日(むなのか)
以降も、7日ごとに法要を行います。それぞれ以下の意味を持ちます。(省略されることが多いですが、菩提寺や宗派によっては丁寧に行うこともあります)
死後の世界では故人の生前の罪について審判を受けているとされており、それぞれの法要をつかさどる十三仏がおります。
元々は中国で十王信仰が死者供養に取り入れられており、この考えが日本に入ってきた際に十王信仰を参考に日本で取り入れられたのが、十三仏信仰となります。
四十九日までの法要を司る仏様は以下となります。
七日(7日目):第1の審判 不動明王
二七日(14日目):第2の審判 釈迦如来
三七日(21日目):第3の審判 文殊菩薩
四七日(28日目):第4の審判 普賢菩薩
五七日(35日目):第5の審判 地蔵菩薩
六七日(42日目):第6の審判 弥勒菩薩
七七日(四十九日):第7の審判 薬師如来
これらの法要では、僧侶の読経を通じて、遺族が供養の気持ちを伝えます。親族が集まって行うことは少なく、僧侶の読経のみで行われるケースが多いです。
七七日(四十九日/しじゅうくにち)[49日目]
49日目、つまり満中陰(まんちゅういん)は、故人の魂が最終審判を受け、極楽浄土へ旅立つとされる重要な日です。仏教においては、忌明けの法要とされ、多くの親族や関係者が集まり、盛大に供養が行われます。この日にあわせて、
本位牌の用意と開眼供養
納骨式
香典返しの準備
なども進められます。
四十九日法要を避けた方がいい日はあるのか
葬儀や告別式の日に、六曜の「友引」は避けた方がいいという風習がありますが、四十九日などの法要に関しましては特に気にする必要はありません。
また、四十九日の法要が3ヶ月またがることは「三月掛け(みつきがけ)」と呼ばれ、「始終苦労が身につく」という語呂合わせから縁起の悪いものとして避けられることがありますが、単なる語呂合わせなので気にする必要はあまりありません。
四十九日までにやるべき準備と手続き一覧
四十九日は「忌明け」の重要な節目であり、多くの準備が必要です。以下は、代表的なやるべきことのチェックリストです。
- ●菩提寺・僧侶への連絡
まずはお世話になっているお寺へ、四十九日法要の依頼をします。日程や読経の依頼、準備すべき供物や供花についても確認しましょう。
- ●日程・会場の決定
四十九日は亡くなってから49日目またはその直前の週末に設定されることが多く、親族の都合も考慮して調整します。会場は自宅・菩提寺・斎場・霊園の法要室などがあります。
- ●参列者への案内
親族や近しい友人など、参列をお願いする人に日程や場所を案内します。案内状の郵送または電話での連絡が一般的です。
- ●法要の内容確認
読経の後に会食や納骨式を行う場合は、それぞれの準備を整えておく必要があります。僧侶や会場に詳細を確認しておくと安心です。
- ●会食・返礼品・引出物の準備
法要後の会食を行う場合は、料理店や仕出し業者への手配が必要です。また、参列者への返礼品や引出物も用意します。予算や人数に応じた品を選びましょう。
- ●遺影・位牌の準備
白木位牌(仮位牌)から本位牌へ切り替えるのも四十九日が目安です。本位牌は菩提寺や仏具店で早めに手配しましょう。
- ●仏壇や納骨先の準備
納骨を行う場合は、墓地・霊園・納骨堂などの手配も必要です。仏壇が未設置の場合は、購入や設置も考えましょう。
四十九日が終わった後にやるべきこと
四十九日法要が無事に終わると、ひとつの大きな節目を迎えます。仏教では「忌明け(いみあけ)」と呼ばれ、この日を境に喪に服す期間が終わり、少しずつ日常生活へと戻っていくとされています。
ただし、ここで終わりではありません。法要後にも、いくつか大切な手続きや気配りが必要です。
四十九日の喪主の服装
喪主も遺族も原則的には喪服着用となります。
服装の詳細については喪主の服装ページにて解説しておりますのでご参照ください。
四十九日のお布施
お布施に決まった相場というものはありませんが、失礼のないようにするには実際にいくら包めばよいのか、悩まれる方も多いと思います。
地域性やお寺との関係も影響してきますが、法要のお布施の一般的な相場は葬儀の際の10分の1ほどと言われています。 もし金額について心配な場合は、葬儀と法要の打ち合わせの際に葬儀社やお寺に確認するといいでしょう。
法要後に僧侶が会食にご一緒しない場合は御膳料を、また会場が僧侶のお寺と別の場合はお車代(いずれも5千〜1万円程度)を同時にお渡しします。
ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております