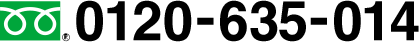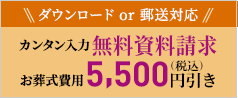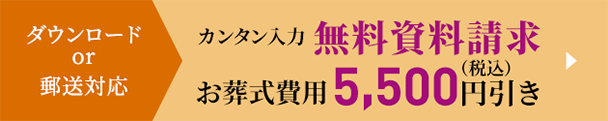お葬式の日程の決め方とは?通夜からの流れや友引・仏滅の注意点
お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
この記事は
「イオンのお葬式」
が書いてます
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
初めての喪主の方へ
- 更新日:2025.12.01
- 初めての喪主の方へ
お葬式の日程の決め方とは?通夜からの流れや友引・仏滅の注意点

身近な方が亡くなられた直後は、深い悲しみの中でさまざまな手続きを進めなくてはなりません。
中でも、お葬式の日程をいつにするかという問題は、多くの要素を考慮する必要がある重要な決め事です。
この流れを事前に把握しておくと、落ち着いて故人を見送る準備ができます。
お葬式の日程の決め方には、火葬場の空き状況や宗教者の都合、親族の予定など、複数の調整が必要です。
この記事では、逝去から葬祭までの一般的な流れと、日程を決める具体的なステップ、そして後悔しないための注意点を詳しく解説します。
逝去当日から何日目?通夜・葬儀の一般的なスケジュール例
故人が亡くなられてからお通夜や葬儀・告別式が何日目に行われるかは、状況によって異なりますが、一般的なスケジュールを知っておくと目安になります。
多くの場合は、亡くなった翌日にお通夜を、その翌日に葬儀・告別式と火葬を執り行う流れとなります。
つまり、逝去された日を1日目とすると、2日目に通夜、3日目に葬儀・告別式という日程です。
ただし、これはあくまで一例であり、火葬場の空き状況や友引などの六曜、宗教者の都合によって日程がずれることも少なくありません。
逝去当日〜翌日:ご逝去から安置まで
ご逝去後、まず医師から死亡診断書を受け取ります。
この書類は役所への死亡届の提出や火葬許可証の申請に必要不可欠なため、必ず受け取りましょう。
次に、事前に決めていた葬儀社、あるいは病院から紹介された葬儀社へ連絡を入れます。
葬儀社が到着したら、寝台車でご遺体を自宅や斎場の安置施設へ搬送し、安置します。
この安置の段階で、葬儀社と葬儀の日程や内容についての具体的な打ち合わせを開始するのが一般的な流れです。
故人がお亡くなりになった当日から翌日にかけては、悲しむ間もなくこれらの手続きに追われることが多いです。
逝去から2日目:通夜
逝去から2日目には、通夜を執り行うのが一般的なスケジュールです。
通夜に先立ち、故人の身を清めて死装束を整え、棺にご遺体を納める「納棺の儀」が行われます。
この儀式は、遺族が故人と過ごす大切な時間となります。
通夜は通常、夕方から始まり、僧侶による読経や焼香、喪主の挨拶、そして参列者への通夜振る舞いという流れで進みます。
夜通し灯りを絶やさず故人を見守るのが本来の形ですが、近年では1〜2時間程度で閉式する「半通夜」が主流です。
この日に、遠方からの親族や一般の弔問客が訪れることが多くなります。
逝去から3日目:葬儀・告別式と火葬
逝去から3日目には、葬儀・告別式と火葬が執り行われます。
午前中から始まることが多く、葬儀は宗教的な儀式として故人の冥福を祈る時間であり、告別式は親しかった人々が最後のお別れをする社会的な儀式です。
式が終わると、棺に花などを手向ける「お別れの儀」を行い、霊柩車で火葬場へ向かいます。
火葬には1〜2時間ほどかかり、その間遺族は控室で待機します。
火葬が終わると、遺骨を骨壷に納める「骨上げ(収骨)」を行い、すべてが終了した後に精進落としの会食を開くこともあります。
この一連の流れをもって、葬儀は一段落となります。
お葬式の日程を決める4つのステップ
お葬式の日程がいつ決まるかは、いくつかの確認事項を順に進めることで確定します。
故人が亡くなられてから葬儀社と打ち合わせを始めますが、すぐに日程が決まるわけではありません。
火葬場の予約状況や宗教者の都合など、外部の要因に大きく左右されるためです。
これらの関係各所の予定を確認し、親族の都合も考慮しながら最適な日程を調整していく必要があります。
ここでは、お葬式の日程を決めるための具体的な4つのステップを順番に解説します。
ステップ1:葬儀社と打ち合わせを行う
最初に行うべきことは、葬儀社との打ち合わせです。
ご遺体を安置した後、喪主を中心に遺族と葬儀社の担当者が集まり、葬儀全体の方向性を決めます。
この打ち合わせでは、まずどのような形式(一般葬、家族葬、一日葬など)で葬儀を行いたいか、おおよその参列者数、そして予算などの希望を伝えます。
これらの要望をもとに、葬儀社の担当者は具体的なプランや見積もりを提示します。
この段階で葬儀の全体像を固めることが、後の火葬場や斎場の予約、宗教者との調整をスムーズに進めるための基盤となります。
担当者と密に連携を取り、不明な点は遠慮なく質問することが重要です。
ステップ2:火葬場の予約状況を確認する
葬儀の日程を決める上で最も重要なのが、火葬場の予約状況の確認です。
火葬場の予約が取れなければ、通夜や告別式の日程を組むことができません。
特に東京をはじめとする都市部では火葬場が混み合っており、希望の日時に予約が取れず数日間待たなくてはならない「火葬待ち」が発生することも珍しくありません。
一方で、札幌などの地方都市では比較的予約が取りやすい場合もありますが、友引の翌日などは混雑する傾向にあります。
葬儀社が遺族の希望を聞きながら火葬場の空き状況を確認し、予約を代行してくれるのが一般的です。
この火葬場の予約が確定した時点で、葬儀全体のスケジュールが具体的に見えてきます。
ステップ3:宗教者(菩提寺など)の都合を伺う
菩提寺がある場合や、特定の宗教者に依頼したいと考えている場合は、その宗教者の都合を確認することが不可欠です。
仏式の葬儀では、通夜や葬儀・告別式で僧侶に読経を依頼します。
そのため、火葬場の予約と並行して、僧侶のスケジュールを早めに確認し、依頼する必要があります。
お盆やお彼岸の時期、あるいは週末などは法務で多忙なことが多く、希望の日時に都合がつかない可能性も考えられます。
もし菩提寺が遠方にある場合や、都合がどうしても合わない場合は、葬儀社に相談すれば同じ宗派の僧侶を紹介してもらうことも可能です。
宗教儀礼を重んじる場合は、この調整が日程決定の重要な要素となります。
ステップ4:親族や主な参列者の予定を調整する
火葬場と宗教者の都合がついたら、次に親族、特に遠方に住んでいる方や高齢の方、故人と縁の深かった主な参列者の予定を確認し、調整します。
全員の都合を完璧に合わせることは難しいかもしれませんが、故人とのお別れに立ち会ってほしい人々の予定はできる限り考慮したいものです。
特に、火葬や骨上げまで参列してほしい近親者には、早めに日程の候補を伝え、参加の可否を確認することが大切です。
近年は家族葬が増えていますが、それでも親族間の連絡と調整は欠かせません。
この最終調整を経て、通夜、葬儀・告別式の日時が正式に決定し、関係者への訃報連絡に進むことになります。
後悔しないために!お葬式の日程調整で注意すべき5つのポイント
お葬式の日程を調整する際には、関係者のスケジュールを合わせるだけでなく、いくつか注意すべき点が存在します。
これらのポイントを見過ごしてしまうと、後から「こうすれば良かった」と後悔したり、関係者に余計な負担をかけてしまったりする可能性があります。
六曜のような古くからの慣習や、火葬場の休業日、地域ごとの風習など、事前に知っておくべき知識は少なくありません。
ここでは、スムーズで悔いのない日程調整を行うために、特に注意すべき5つのポイントを具体的に解説します。
ポイント1:「友引」にお葬式を避けるべき理由
日本のカレンダーには「六曜」という暦があり、その中の一つである「友引」の日は、お葬式を避けるのが一般的です。
友引はもともと「共引き」と書き、勝負事で引き分けになる日とされていましたが、字面から「友を冥土へ引く」と解釈されるようになりました。
この迷信から、葬儀・告別式を友引に行うことは避けられる傾向にあります。
ただし、これはあくまで慣習であり、宗教的な意味合いはありません。
そのため、お通夜を友引に行うことは問題ないとされています。
しかし、この慣習に合わせて友引を休業日とする火葬場が多いため、結果的に友引とその翌日は葬儀の日程を組むのが難しくなることが多いのが実情です。
ポイント2:火葬場が休業している日に注意する
葬儀の日程を決める際、火葬場の休業日を把握しておくことは非常に重要です。
多くの公営火葬場では、友引を休業日として定めています。
そのため、友引の日には火葬を行うことができず、葬儀・告別式の日程もその日を避けて組む必要があります。
また、友引以外にも、年始(1月1日〜3日)や施設のメンテナンス日を休業日としている場合があるため、事前の確認が不可欠です。
地域によっては、友引ではなく仏滅を休業日としているケースも存在します。
これらの休業日を考慮せずに日程を計画すると、後から大幅な変更を余儀なくされる可能性があるため、葬儀社を通じて最新の情報を確認することが大切です。
ポイント3:地域独自の風習や慣習も確認しよう
お葬式の日程や流れには、全国共通のルールだけでなく、地域独自の風習や慣習が根強く残っている場合があります。
例えば、通夜の前に火葬を行う「前火葬」の地域と、葬儀・告別式の後に火葬を行う「後火葬」の地域があります。全国的には後火葬が一般的ですが、一部地域では前火葬が主流です。
具体的には、東北地方や北海道の一部地域で前火葬が一般的であり、関東地方においても、茨城県や千葉県の一部、東京都西部のあきる野市や日の出町周辺地域などで前火葬が行われることがあります。
また、通夜の振る舞いの内容や、出棺時の儀式などにも地域差が見られます。故人が生まれ育った地域の慣習を尊重したい場合は、地元の事情に詳しい葬儀社や地域の年長者に相談し、風習を確認しながら日程や段取りを決めていくことが望ましいです。
ポイント4:年末年始や大型連休の日程調整
年末年始やゴールデンウィーク、お盆休みなどの大型連休中にご不幸があった場合、日程調整は通常よりも難しくなる傾向があります。
多くの火葬場は1月1日から3日まで休業するため、その期間は火葬が行えません。
結果として、休業明けに予約が集中し、数日間の「火葬待ち」が発生しやすくなります。
また、親族が帰省や旅行で不在にしているケースも多く、参列者の予定を合わせるのが困難になることも考えられます。
同様に、異動や引越しが多い年度末の3月や新年度が始まる4月も、人の動きが活発になるため、日程調整に配慮が必要な時期です。
こうした時期に葬儀を行う場合は、通常より日数がかかる可能性を念頭に置いておく必要があります。
ポイント5:ご遺体の状態を保つための安置方法
火葬場の混雑やその他の事情で、ご逝去から火葬までの日数が長引く場合には、ご遺体の状態を適切に保つための処置が不可欠になります。
通常、ご遺体の腐敗を防ぐためにはドライアイスを使用しますが、安置期間が数日以上に及ぶと、ドライアイスの追加が必要になり費用がかさむことがあります。
また、より長期間、そして生前の姿に近い状態で安置したい場合には、「エンバーミング」という選択肢もあります。
これは、専門の技術者(エンバーマー)がご遺体に防腐・殺菌処置を施す方法です。
どちらの方法を選択するかは、安置日数やご遺体の状態、費用などを考慮して、葬儀社とよく相談して決めることが重要です。
葬儀形式ごとの日程の違いを解説
お葬式の日程は、選択する葬儀形式によっても変わってきます。
伝統的な一般葬や家族葬では、通夜と告別式を2日間にわたって行いますが、近年では儀式を1日で済ませる一日葬や、儀式を行わない直葬(火葬式)を選ぶ人も増えています。
これらの形式は、儀式の内容だけでなく、逝去から火葬までに要する日数やスケジュールも異なります。
それぞれの葬儀形式がどのような流れで進むのか、日程にどのような違いがあるのかを理解しておくことで、故人や遺族の意向に最も合ったお見送りの形を選ぶことができます。
家族葬や一般葬の場合
家族葬や一般葬は、最も一般的な葬儀形式であり、通夜と葬儀・告別式を2日間にわたって執り行います。
通常、ご逝去された翌日の夕刻に通夜を行い、その翌日の日中に葬儀・告別式、そして火葬という流れになります。
逝去日を1日目とすると、2日目に通夜、3日目に葬儀・告別式と火葬を行うのが基本的なスケジュールです。
ただし、これは火葬場や宗教者の都合がスムーズについた場合の最短日程です。
実際には、火葬場の予約状況や友引を避けるなどの理由で、逝去から4〜5日後、あるいはそれ以降に葬儀が行われることも少なくありません。
準備や会葬者への対応など、喪主や遺族が関わる時間も長くなる傾向があります。
一日葬の場合
一日葬は、通夜を行わず、葬儀・告別式から火葬までを1日で執り行う形式の葬儀です。
遠方からの参列者や高齢の遺族の身体的な負担を軽減できるという利点があります。
日程の流れとしては、ご逝去の翌日に納棺などを行い、翌々日の日中に葬儀・告別式と火葬を済ませます。
通夜がないため、拘束時間は短縮されますが、準備期間については一般葬と大きく変わりません。
なぜなら、法律で定められた通り死後24時間は火葬ができないため、ご逝去当日に葬儀を行うことはできないからです。
結果的に、ご遺体の安置期間は一般葬の場合と同程度になることがほとんどです。
直葬(火葬式)の場合
直葬(火葬式)は、通夜や葬儀・告別式といった宗教的な儀式を行わず、火葬のみで故人を見送る最もシンプルな形式です。
法律で定められている「死後24時間以内の火葬はできない」という規定を守ればよいため、ご逝去の翌日には火葬を行うことが可能で、日程的には最短で済みます。
ごく限られた近親者のみで、火葬炉の前で簡単なお別れをしてから火葬に臨むのが一般的な流れです。
儀式がないため、費用を大幅に抑えられるほか、遺族の精神的・肉体的な負担も少なくなります。
ただし、菩提寺がある場合は事前に相談しないと納骨を断られるなどのトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。
葬儀後に行う法要の日程も確認しておこう
お葬式が無事に終わっても、故人を供養するための儀式は続きます。
仏式の場合、葬儀後には初七日や四十九日といった重要な法要・法事があります。
これらの法要の日程についても、葬儀の打ち合わせの際に葬儀社や僧侶と相談し、あらかじめ決めておくと後の段取りがスムーズになります。
特に遠方に住む親族がいる場合は、葬儀の場で今後の法事の予定を伝えておくと、参列の調整がしやすくなります。
葬儀後の慌ただしさの中で日程を決めるのは大変なため、先を見越して準備を進めておくことが大切です。
初七日法要はいつ行う?
初七日法要は、故人が亡くなった日(命日)から数えて7日目に行う、最初の重要な法要です。
仏教では、故人の魂が三途の川のほとりに到着するのがこの日とされています。
しかし、現代では葬儀から間もない時期に親族が再び集まるのが難しいという事情から、本来の日程で初七日法要を行うケースは減少しています。
その代わりとして、葬儀・告別式の当日に法要を繰り上げて行うのが主流となっています。
火葬後に会食の席(精進落とし)で執り行う「繰り上げ初七日」や、葬儀・告別式の式中に組み込んでしまう「式中初七日」といった形が一般的です。
四十九日法要の日程の決め方
四十九日法要は、故人の命日から数えて49日目に行われる法要で、「満中陰(まんちゅういん)」とも呼ばれ、忌明けの節目となる非常に重要な儀式です。
仏教の教えでは、この日に故人の来世の行き先が決まるとされています。
この法要をもって遺族は忌服期間を終え、日常生活に戻ります。
日程の決め方としては、親族が集まりやすいように、49日目当日か、それよりも前の土曜日や日曜日に行うのが一般的です。
49日を過ぎてから法要を行うのは良くないとされているため、日程は必ず前倒しで調整します。
この日に合わせて納骨式を行うことも多いため、早めに日程を確定させ、会場や僧侶の手配、参列者への案内を進める必要があります。
お葬式の日程に関するよくある疑問と回答
初めてお葬式を執り行う際には、日程の決め方一つをとっても、さまざまな疑問や不安が生じるものです。
「訃報の連絡はいつ誰にすればいいのか」「お坊さんの都合がつかない時はどうしよう」「法律で何か決まりごとはあるのか」など、細かい点まで気にかかるかもしれません。
ここでは、そうしたお葬式の日程に関して多くの人が抱きがちな疑問点について、Q&A形式で分かりやすく解説します。
事前に知識を得ておくことで、いざという時に落ち着いて対応できるようになります。
Q. 訃報の連絡はどのタイミングでするべき?
訃報の連絡は、伝える相手との関係性によってタイミングを分けるのが一般的です。
まず、家族や三親等以内の親族など、ごく近しい身内には、ご臨終後すぐに電話で連絡します。
次に、葬儀の日程や場所が決まった段階で、故人と特に親しかった友人や、勤務先・学校関係者、町内会などに連絡を入れます。
この際、伝える内容は相手に応じて調整し、葬儀の形式が家族葬で一般の参列を辞退する場合は、その旨も明確に伝えることが重要です。
連絡手段は、緊急性の高い近親者へは電話が基本ですが、それ以外の方へはメールやSNSのメッセージ機能などを活用しても差し支えありません。
Q. 宗教者の都合が合わない場合はどうしたらいい?
菩提寺の住職など、特定の宗教者に依頼したい場合、その方の都合がどうしても合わないこともあります。
まず試みるべきは、葬儀の日程自体を宗教者の都合に合わせて調整することです。
しかし、火葬場の予約状況などから日程の変更が難しい場合は、いくつかの対処法が考えられます。
一つは、菩提寺に相談し、同じ宗派の別の僧侶を紹介してもらう方法です。
多くの場合、近隣の寺院などから代理の僧侶を手配してもらえます。
また、菩提寺がない場合や、紹介が難しい場合は、葬儀社に相談することで、希望する宗派の僧侶を手配してもらうことも可能です。
Q. 法律で火葬までの期間は決まっている?
法律で火葬までの期間について最低限のルールが定められています。
「墓地、埋葬等に関する法律」の第3条により、「死産の場合を除き、死亡または死産後24時間を経過した後でなければ、埋葬または火葬を行ってはならない」と規定されています。
これは、万が一にも蘇生の可能性があることや、死亡診断の誤りを防ぐための措置です。
このため、どんなに急いでも、亡くなってから24時間以内に火葬することはできません。
一方で、火葬までの期間に法律上の上限はありません。
火葬場の混雑や遺族の都合により、数日間から1週間以上経ってから火葬を行うこともあり、その場合はご遺体を適切に安置・保全する処置が必要になります。
まとめ
お葬式の日程を決めるプロセスは、故人が亡くなられた直後から始まり、複数の要素を同時に調整していく必要があります。
最も重要なのは火葬場の予約状況で、これを基点に宗教者の都合や親族の予定を組み合わせていきます。
また、友引や火葬場の休業日、地域独自の慣習といった注意点も考慮しなくてはなりません。
葬儀の形式によってもスケジュールは異なります。
この複雑な調整作業を円滑に進めるためには、信頼できる葬儀社と密に連携を取ることが不可欠です。
疑問や不安な点があれば、すぐに葬儀社の担当者に相談し、一つひとつ確認しながら進めることで、故人を心安らかに見送るための準備を整えられます。
ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております