通夜(つや)
葬式の前夜、親族や知人が亡き人の霊を守り、慰めることをいう。死亡から葬儀までの間二夜をおくるときには、死亡当日の夜は、仮通夜にして、本通夜は翌日に営まれます。昔は近親者によって営まれましたが、現在は、死者に対する社会的儀礼として、関係を持つものは、通夜の...

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
葬式の前夜、親族や知人が亡き人の霊を守り、慰めることをいう。死亡から葬儀までの間二夜をおくるときには、死亡当日の夜は、仮通夜にして、本通夜は翌日に営まれます。昔は近親者によって営まれましたが、現在は、死者に対する社会的儀礼として、関係を持つものは、通夜の...

追善供養は死者の冥福を祈って、遺族をはじめとする縁者が、善事を後から行うこと。七七忌の法事などを意味します。七七忌は十一世紀の前半頃に上流社会で行われていました。百か日、一周忌、三回忌は中国の風習を習ったものです。三十三回忌は鎌倉時代、二十五回忌は室町時...

血族関係のある子や孫などを直系卑族、父や母、あるいは祖父母を直系尊属といいます。相続の場合、民法は相続人を2つに大別しています。1つは被相続人と血縁があることで相続が認められる人で、これを血族相続人といいます。もう1つは血のつながりはないが、配偶関係にあ...

死者の遺族を尋ね、お悔やみを述べること。遺族は、弔問客の挨拶を受けますが、通夜または葬儀当日に弔問客を玄関に迎えたり、見送ったりしなくても失礼にあたりません。特に喪主は遺体のかたわらについて、弔問の挨拶を受けます。一方、初めての弔問の場合「このたびはご愁...

弔問や葬儀に参列できない場合に打つ、お悔やみの電報。電報は局番なしの115でかけ、宛名は普通喪主にします。電文の例文は、「謹んで哀悼の意を表します」「ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます」「ご尊父様のご逝去を悼み謹んでお悔やみ申し上げます」「ご逝去の...

手水の義は、神道の祭儀の前に行われる重要なもので、これを済ませてから席につきます。柄杓ですくった水は、三度に分けて注ぐのが正しい作法です。自分で水を掛けるときは、まず左手を清め、次に右手を、次に左手に水を受けて口をすすぎ、さらに最後に左手を洗い、紙を使い...

葬儀のさいに披露する、死者への最後の別れの言葉。ないようには 1.故人への追悼 2.故人の生前業績を讃える 3.残されたものの決意を述べる、という構成です。弔辞は会社関係の中で、故人と親睦のあつかった人に依頼します。奉書か巻紙に毛筆で書き、末尾から短冊形に折り...

中有ともいい、死んだ後、次の生を受けるまでの間の状態を言う。この間死者の魂は、三界、六道をさ迷うといわれますが、喪家では物忌みの期間として忌の生活を営みます。一般に中陰の終わる日 (満中陰)は四十九日です。「宙に迷う」とは、中有の間、死者の霊がさ迷っている...

壇引きとも言います。葬式のあとに祭壇を片付けること。そのあとに中陰壇を設置し、遺影を置いておまつりします。a

死者および、遺族が所属している寺院。菩提寺。もともと梵語「ダーナ」は布施を意味し、布施を施す対象であるお寺のことを指します。

ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております

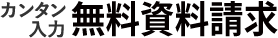

地図から葬儀場を探す