経机(きょうづくえ)
経典を置いたり、読誦の時に用いる机。前机。経卓 (けいしょく)とも言い、禅宗では経案 (きんあん)とも言います。

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
経典を置いたり、読誦の時に用いる机。前机。経卓 (けいしょく)とも言い、禅宗では経案 (きんあん)とも言います。

死者に着せる経の書かれた白い着物。背には南無阿弥陀仏などと書く。経帷子は数人で分担して縫い、縫い糸は止め結びをしないといいます。

仏前や死者の前に花を供えること。形として花束、花環、籠に盛り付けたものなどがあります。釈尊が成道時には、さまざまな天の宝花が空から降り、釈尊を供養したといいます。

日本でいう「棺」のこと。キャスケットは「宝石の小箱」「貴重品入れ」から転じた言葉で、土葬用の装飾された立派な棺のことをいいます。欧米では、木棺だけでなく、大理石などで作られたさまざまな種類のキャスケットがある。

死者の遺族が、一定の期間喪に服するならわし。忌服の期間は、故人の続柄によって異なり、父母が死亡した場合の忌日は50日、服喪は13ヶ月と一番長く、以下夫、妻、子、兄弟姉妹の順となります。一般には仏教のしきたりに従って、忌の期間は、死後四十九日、服の期間は1...

喪家の入口に「忌中」と書いて貼る札。入口に簾を裏返しにして垂らし、墨で黒枠を付け、中央上部に忌中と書くのが多いようです。なお、通夜、葬儀・告別式の日時が決まったら「忌中」の下に書き添えます。

仏式では、死者を安置するさい、北に頭を向ける。この由来は、釈尊が入滅するとき、頭を北向きにし、額を西の方に向き、右脇を下に寝ていた故事にならったものとされています。北枕が困難な場合には、西枕にします。

仏を信じ、その教えに従うこと。仏にすべてを捧げること。帰依の原語はナマスで、漢字で「南無」と書きます。従って、「南無阿弥陀仏」は阿弥陀仏に帰依しますという意味になります。

四十九日目の忌明け (満中陰)に行う法要。中陰の期間には死者が善処に生まれることを願って、七日ごとに仏事を行うが、忌明け法要はその期間の最後の法要となります。日本でも756年の聖武天皇崩御のとき、七七斎会を修したことが記録されており、17世紀ごろから四十九...

頭頂に水を注ぐこと。あるいは霊の供養のため、墓石に柄杓で水を注ぎかけること。昔インドで国王の即位のとき、水をその頭頂に注ぎかけた儀式に由来します。灌頂は密教の儀式の一つで、仏位を継承するさいに行います。

ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております

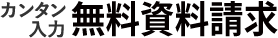

地図から葬儀場を探す