玉串奉奠(たまぐしほうてん)
榊の枝に紙垂をつけたものを用い、神前に敬意を表し、神意を受けるために、祈念を込めて捧げるもの。神式の告別式にあたる (葬場祭)では、弔辞・弔電披露の後、斎主、喪主の順で玉串の奉奠を行います。

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
榊の枝に紙垂をつけたものを用い、神前に敬意を表し、神意を受けるために、祈念を込めて捧げるもの。神式の告別式にあたる (葬場祭)では、弔辞・弔電披露の後、斎主、喪主の順で玉串の奉奠を行います。

食べ物を盛る脚付きの台。神饌を盛るさいに使います。また仏前の左右に置き、果物を入れて供える脚の高い器も高月といいます。木製で漆塗りのもの、金箔を押したプラスチックのものなどがあります。

忌日の前夜とか年忌の前夜をいう。この夜には僧侶を招いて、位牌を飾り、故人の冥福を祈る風習がありますが、現在は行われていません。

安らかに死ぬこと。少しも苦しみのない往生。天寿を全うすること。

祖先の霊。御霊をいう。死者の霊は肉体から離れたあとも、生前の個性を保っているが、盆ごとに生家を訪れて子孫の供養を受け、三十三回忌ないし五十回忌の弔い上げによって、集合体としての祖先霊として扱われます。

死者の供養塔や墓標として伝えられ、頭部に五輪形を刻み、梵字などを記した板木。釈尊の遺骨を納めた仏塔である「ストゥーパ」が音訳されたもの。卒塔婆には経文や戒名、施主の名を書き、年回供養やお彼岸、お盆などに板塔婆を立て、墓前で読経してもらいます。

葬儀のさい遺族側が、会葬者の焼香のあと、謝意をあらわすために渡す品のこと。通常ハンカチ、タオル、石鹸など、会葬礼状に添えてお渡しします。

禅宗三派の一つ。宗祖道元は入宋して法を受け、帰国後、永平寺を開きました。主著に「正法眼蔵」があり、越前の永平寺と鶴見の総持寺を大本山とします。本尊は釈迦牟尼仏で経典は「修証義」、「般若心経」などです。

葬儀の進行の手配、指示を中心となって行う人。個人葬では、町内会長、団地の自治会長などがなるのが通例です。社葬では、社長や個人の友人で肩書きのある人が委員長になります。葬儀予算を、喪主や遺族と相談し、実務を執行するさいに、いろいろな係を決め、そのまとめ役を...

禅定を根本とする仏教の宗派。日本では臨済宗、曹洞宗、黄檗宗の三宗を総称して禅宗といいます。鎌倉初期に栄西とその弟子の道元が、宋の禅を日本に伝えました。栄西は臨済宗、道元は曹洞宗の開祖。黄檗宗は江戸時代に、明の隠元によって日本に伝えられました。

ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております

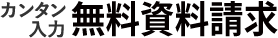

地図から葬儀場を探す