神道(神式)の葬儀・神葬祭
神道について(例:出雲大社系神社) 神道には仏式のような教義経典などはなく、神社によってご祭神も違うことなどから、その地域や神社によって祭式や祭事の進め方に相違があります。このページでは出雲大社系神社を例としてご説明いたします。 ご祭神 ...

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
神道について(例:出雲大社系神社) 神道には仏式のような教義経典などはなく、神社によってご祭神も違うことなどから、その地域や神社によって祭式や祭事の進め方に相違があります。このページでは出雲大社系神社を例としてご説明いたします。 ご祭神 ...

葬儀の流れ・手順 葬儀は仏教でいうところの亡くなられた方が浄土へ旅立たれるための大切な儀式です。また、ご遺族にとっては大切な人の死を乗り越えるための儀式であります。一方で、亡くなった直後から心癒される間もなく、慣れない事柄を決定していく作業は、喪主やご家...

納棺あるいは、出棺時に死者に手向ける花。棺の蓋を開け、葬儀に供えられた花を遺体の周囲に飾ります。この最後の対面は、遺族、近親者で行います。また棺には故人の愛用の遺品を入れ、棺の蓋をします。

キリスト教・教会式について プロテスタント葬儀概要 原則としてイエスキリストは神の子であると信じ、三位一体の人格神であることを認めた者が、キリスト教葬儀を切望するケースが多いです。しかし、信仰を持っていない場合でも主イエスは「私に反対しない者は私の味...

「南無阿弥陀仏」の六文字のこと。浄土宗、浄土真宗で本尊のかわりにおまつりします。また法事のときには「南無阿弥陀仏」の名号の掛け軸を、掛ける場合があります。

三途の川の渡し賃として、死者の棺の中に入れるお金。六道銭ともいいます。中国でも納棺する前に、黄色の布袋に経文や仏像の画や紙銭を集め、死者の首に掛ける風習があります。

仏教歌謡の一種で、仏・菩薩の教えや功徳、高僧の業績をたたえる歌。日本後で歌われるために和讃と呼ばれます。平安時代に発し、親鸞には「浄土和讃」「高僧和讃」「正像末和讃」などがあります。現在法要で和讃を多く使うのは真宗で、親鸞の和讃を抜粋し、念仏と組み合わせ...

仏教の世界観で、すべての人が、死ねばその生前の行いに従って、迷いの世界に車輪のように果てしなくめぐりさ迷うこと。六道は下から、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天上を言います。日本では死後の世界を六道とすることから、墓地を六道原という所があり、京都東山の鳥...

遍照金剛というのは、空海の金剛名であり、この一句は、弘法大師空海に帰依するの意。弘法大師が唐に留学して、真言密教の秘奥をきわめ、師の恵果から頂いた称号が遍照金剛の名号です。四国四十八箇所霊場を巡るお遍路はこの名号を唱えます。

浄土宗について 宗名 浄土宗 元祖 法然上人 西暦1133年 4月7日 降誕 西暦1212年 1月25日 往生 本山 総本山知恩院 主尊 阿弥陀如来(阿弥陀仏) 名号 南無阿弥陀佛 よく読まれるお経 浄土三部経(阿弥陀経・無量寿経・観無量...

ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております

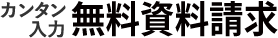

地図から葬儀場を探す