自然死(しぜんし)
いわゆる老衰。全身の諸臓器が老化して死に至ること。外因死が除外され、かつ死因となるべき疾病が見出せなかった死体。死亡診断書(死体検案書)の死亡の種類の欄に「病死および自然死」という欄があります。

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
いわゆる老衰。全身の諸臓器が老化して死に至ること。外因死が除外され、かつ死因となるべき疾病が見出せなかった死体。死亡診断書(死体検案書)の死亡の種類の欄に「病死および自然死」という欄があります。

七七日忌とも言う。人の死後、次世の生を受けてない七の七倍の期間。人の死後四十九日間は中有 (ちゅうう)に迷っているため、死者のために追善供養をして冥福を祈り、死者が果報を得て成仏するように、初七日から七日ごとに供養する習慣があります。「十王経」には、中有の...

仏前に捧げられるもくれん科の常緑樹。しきびとも言われます。仏事ではこの樒をハナと称し、墓や位牌の前に水と一緒に供えます。特に埋葬や納骨のときには一本花といって一本の樒を供える風習があります。

葬具の一つ。白紙を竹串に巻きつけ、横に細かくハサミを入れたもの。かつてはこれを四本、木の台や大根の輪切りに突き立て近親者が持って葬列に加わりました。四華の由来は、釈尊が、涅槃に入られるとき、死を痛み悲しんで四本の沙羅双樹の花が白く変化したことから、それに...

角形の折敷 (おしき)に、前と左右の三方に穴の空いた台。ひのきの白木で作られ、儀式のとき神饌をのせるのに用います。

神社・寺院・神棚の神・仏を拝むこと。神棚に参拝するときは、まず手を清め、口をすすぎ、お供えします。そして二礼 (二度深くお辞儀をする)二拍手一礼します。

人が死んであの世に行く途中、初七日に渡るという川。葬頭河 (しょうずか)とも三つ瀬河とも言います。人が死ねばこの河を越さなければならないが、川の瀬に緩急の異なる三途があって、生前の罪の軽重によってこの三途のうちの一つを渡るといいます。

つばき科の常緑高木。枝葉はしばしば依代 (よりしろ)として神式葬祭に用いられます。玉串もその一つです。

冥土にあるとされる河原。中世に出た「賽の河原の地蔵和讃」によれば、母親の生みの恩に報いないで死んだ子供は、その罪で賽の河原に行き、刑罰を受けるといいます。子供たちは、河原の石を積み重ねて塔を作ろうとするが、地獄の番人がやってきて、鉄の棒でそれを突き崩します...

仏教の祭壇は、仏・菩薩、死者や故人の供養のための壇です。形態的には常設の祭壇と、仮説の祭壇があります。常設のものは寺院仏堂内の仏像を安置する須弥壇や家庭用の仏壇があります。仮説のものとしては、葬儀用祭壇、四十九日までの中陰壇、また盆に使う精霊棚があります...

ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております

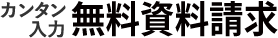

地図から葬儀場を探す