野辺の送り(のべのおくり)
死者を火葬場や埋葬場まで、つき従って送ること。またその行列。現代では、火葬場まで関係者がハイヤーに分乗して、霊柩車に従っていく場合がほとんどです。

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして用語集など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひご活用ください
葬儀では普段耳慣れない言葉が多く、
独自の作法や意味を持つものもあります
慌てないためにも、私たち「イオンのお葬式」が
わかりやすくご紹介します
死者を火葬場や埋葬場まで、つき従って送ること。またその行列。現代では、火葬場まで関係者がハイヤーに分乗して、霊柩車に従っていく場合がほとんどです。

仏式の納骨式では、まずお骨を墓の中に安置し、遺族、近親者の手で土をかけて埋葬します。納骨が終わると、僧侶の読経の中で一同で焼香します。最近の墓では、コンクリートで納骨室が作られていて、お骨を納めて蓋をするだけでよいところもあります。納骨堂に納める場合には...

死体を火葬にした後、骨上げしたお骨を納骨堂あるいはお墓に納めることをいいます。

遺体を棺に納めること。僧侶によって納棺経を上げてもらい、読経の中で納棺することもあります。納棺のさい、死者が生前大切にしていたもので、燃えやすいものを選び一緒に入れます。ふたの上には、金襴の布をかけておきます。

「南無阿弥陀仏」と唱えること。念仏には日常となえる尋常行儀、特定のときに唱える別時行儀、そして死に臨んで浄土に迎えられるようとして唱える臨終念仏があります。

忌日に法要を営み、故人の冥福を祈ること。死亡した翌年の祥月命日に一周忌を行い、一周忌の翌年に三回忌を行います。その後、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌、百回忌とあります。

釈迦が沙羅双樹の下で涅槃に入るときの様。即ち頭北面西脇臥で、周囲に菩薩をはじめ弟子たちが取り巻いている図。

すべての煩悩の火が焼き尽くされた、不生不滅の境地。悩みや苦しみを離れた悟りの境地。釈尊の入滅を涅槃といい、やがて悟りの意味に転用されました。

日蓮正宗とは、富士門流ともいわれ、日蓮宗の一派。日蓮宗の僧侶、日興が開祖。静岡県富士宮市の大石寺を本山とし、板本尊を本尊とします。

死者が出た喪家で、最初に迎える盂蘭盆会のこと。初盆。普段のお盆より、お飾りやお供えを盛大にして、おまつりするしきたりがあります。新盆には、親類縁者が盆提灯やお飾りを供えて、しめやかに故人を偲ぶならわしも残っています。

ちょっとした疑問やお悩みも多数
ご相談いただいております

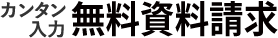

地図から葬儀場を探す